医療問題弁護団・研究会全国交流集会で、札幌に来ています。
この集まりは、全国各地の医療問題弁護団、医療問題研究会が、年に一度、一同に会して、その時々のテーマについて議論し、経験を交流するというもので、わたしたちにとっては、貴重な勉強の機会になっています。
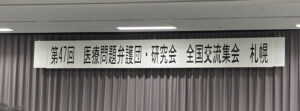
今年の研究発表は、以下の2題。
① 転送義務違反の判例分析(札幌)
② 医療過誤訴訟における相当程度の可能性の検証(東京)
当事務所のかかわった事案では、テーマ①の関係で、CASE15:急性骨髄性白血病で一般病院に入院した25歳女性が、入院3日目に脳出血で死亡した事例、テーマ②の関係で、CASE61:非専門医であっても、ガイドラインの改訂を待つまでもなく、TIAの適切な診断、早期機序確定・診断開始義務があったとして医師の過失が認められた事例が、検討、分析されていました(テーマ①の裁判例集には、CASE06とCASE42も含まれています)。
実は、CASE15は、テーマ②の相当程度の可能性の議論においても興味深い事案で、地裁判決では、過失がなければその時点では生存していた高度の蓋然性を認めながら、予後が厳しいとして慰謝料600万円、その認定額が不当に低いとして控訴したところ、控訴審判決は高度の蓋然性を否定して相当程度の可能性に落としたものの、慰謝料額を900万円に増額したという、ちょっと珍しい事案です。
②についての討論では、その事案を紹介するとともに、相当程度の可能性については、高度の蓋然性の主張とは別に主張が必要なのか、あるいは因果関係についての縮小認定ができるのかという問題を提起させていただきました。
