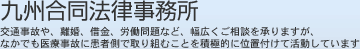取扱事件項目別
九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています
Category主な取扱事件
ハンセン病問題
「ハンセン病問題」をご存知でしょうか。
2001年5月11日の熊本地裁判決から今年で12年が経ち、最近は報道される機会も少なくなったので、ご存じない方もいらっしゃるかと思います。しかし、ハンセン病隔離政策の被害者の人権回復の闘いはまだ続いています。また、日本における基本的人権の保障、医療のあり方に関しても、とても重要な問題提起が含まれており、決して風化させてはならない問題です。
ハンセン病とは
ハンセン病は、らい菌という細菌による感染症です。症状は末梢神経障害が中心です。運動神経が障害されると動きが悪くなり、感覚神経が障害されると痛みを感じなくなります。そのため、手足がとても傷つきやすくなりますし、傷ついても、気がつかないまま悪化させてしまうことも多いようです。また、顔面の神経が障害されると、獅子様顔貌といわれる特徴的な外見を呈するようになります。
この病気が細菌感染症であることを発見したのが、ノルウエーのアルマウエル・ハンセンという医師で、19世紀後半のことです。しかし、これが通説になるにはかなりの時間がかかりました。というのは、このらい菌というのがとても弱い菌で、なかなか感染しないからです。ハンセンのお師匠さんであったダニエルセンという医師は、ハンセンの説に大反対をして、患者の膿を自分に注射して、「ほら、それでもうつらない、こんな感染症があるものか!」と反論したという話があるくらいです。
ただし、いまの医学では、感染力が弱いというよりも、感染はするのだけれどほとんど発病しないのだと説明されています。感染した人のうち、この菌に特殊な免疫応答をする人だけ発病する。この免疫応答には遺伝的要素もあると言われていますが、血友病などと違って、単独の遺伝子ではなく、多くの遺伝子が関与しているため、環境的な要因に大きく影響されるようです。患者が多発しているのは例外なく低開発国、低開発地域であり、日本では新しい患者は発生していません。
戦前の日本では、この病気は不治の病として怖れられましたが、これは、らい菌があまりに弱く、培養ができないために、薬の開発が他の感染症に比べて遅れたことも影響しているようです。プロミンという結核に対する薬がハンセン病にもよく効くということが発見されたのは、1943年のアメリカでのことです。戦争が終わった1945年からは、日本でもプロミンによる治療が始まりました。
日本のハンセン病政策
日本は、このハンセン病に対し、1907年の「癩予防に関する件」という最初の法律以降、一貫して強制隔離政策を採用し、それをなんと1996年まで続けてきました。
1907年の「癩予防に関する件」という法律には、救貧政策的な面もありました。当時、ハンセン病の患者さんたちのなかには、仕事ができなくなり、故郷に住めなくなって、人の集まる神社仏閣とか観光地で物乞いをして暮らしている人もいました。当時、こういう人を「浮浪癩」と呼んでいました。欧米では、そういう人に対して、教会が救いの手を差し伸べます。
日本でも、明治の早い時期に、ハンセン病の療養所をつくったのは、外国からきた宣教師たちでした。こういう状況で、日本政府は浮浪癩を宣教師に任せきりにして放置しているという批判を外国から浴びることになります。当時の日本は、欧米諸国に追いつけ追い越せと頑張ってきて、とうとう日露戦争で大国ロシアをやっつけたと鼻息の荒い頃です。そんな外国の批判に甘んじるわけにはいかない、なんとか浮浪癩対策をやろう、どうやら近頃の知見ではらい病は感染症だというではないか、それなら感染を防ぐためという名目で療養所をつくって、そこに収容してしまえ、という話になり、ハンセン病はうつるから隔離する、場合によっては患者の意思に反して療養所に入れるという制度が始まってしまいました。
こうやってスタートした強制隔離政策は、だんだん自己肥大していきます。それを後押ししたのが、当時の優生思想でした。富国強兵を競う先進諸国の中で生き残っていくためには、軍隊が強いだけではダメ。国民の全てが体力、知力ともに優れている必要がある。優れた遺伝子を残し、劣った遺伝子を排除して、国民全体を優秀なものにしていこう。これが当時の優生思想であり、極端な形としては、ドイツのナチスのユダヤ人政策となってあらわれます。
日本では、この優生思想は、ハンセン病政策に猛威を振るいました。「日本から癩を根絶するためには患者を全て療養所に収容してしまうことだ」という癩根絶策が唱えられ、1万人収容を目指して療養所の建設、増床が行われていきました。その一方で、各県では無癩県運動、つまり、癩患者ゼロ県を目指すという運動が行われ、鵜の目鷹の目で患者狩りが行われました。この運動は日本が日中戦争から太平洋戦争へと深入りしていく1940年前後に最も激しく展開されたようです。
1945年に戦争が終わって、47年には新しい憲法が制定されます。そして、ハンセン病療養所ではプロミンが劇的な効果を上げていました。当然、ここで強制隔離政策は転換されるべきだったのです。
ところが、現実には、1949年頃から、第二次無癩県運動とでもいうべき患者狩りが猛威を振るいます。これは、むしろプロミンを武器とする患者収容運動でした。「療養所にはプロミンがある、プロミン注射で癩は治る」。そういって、敗戦で緩んだ強制隔離政策のタガが締め直されました。療養所の患者たちは、癩予防法の廃止を求めて立ち上がり、いわゆる予防法闘争が展開されました。療養所でのハンガーストライキ、国会での座り込みといった大闘争が展開されたのですが、そこでできたのは、ほとんど内容に変化のない、癩の字がひらがなの「らい」になっただけのような新しい法律でした。
患者たちの被害
このような日本のハンセン病政策は、患者たちに想像を絶する被害をもたらしました。
小学校時代に発病した男性は、度重なる入所勧奨で、ハンセン病であるとのうわさが近所に広まり、自宅を訪れる人はいなくなりました。縁談が破れた姉は、「こんな家にはいたくない」と家出してしまいました。ある日、学校から帰ってきた弟が、「ぼくは病気じゃないよね、ぼくは病気じゃないよね」と泣きながら母親の背中を叩くのをみて、療養所に入ることを決意します。16歳の頃のことです。
ある女性は、入所を避けるために人里離れた山奥の小屋での一人暮らしをしているのに、「どうしても行かなきゃ手錠を掛けていくぞ」、「山狩りをしてでも連れていく」などと執拗に迫られ、自殺も試みるまでに追い込まれた末に入所しています。
入所にあたっては、家畜運搬用の船で運ばれたり、腰縄付きで歩く後から消毒液を噴霧されたり、とうてい人間に対する扱いではありません。
療養所での扱いもひどいものでした。軽症の患者は、療養所を維持するための作業に従事させられました。というよりは、もともとハンセン病療養所には、患者作業なしで維持できるような人員は配置されていませんでした。戦前のことですが、「軽症患者の退所を認めるべきだ」という意見に対して、「それを認めたら療養所は生き地獄になる」と反論した療養所の所長がいます。もちろん、重症患者の世話をする人がいなくなるからです。
草津の栗生楽泉園には「特別病室」という施設があり、全国の療養所から、施設の方針に反抗的な患者が送られてきました。「重監房」と怖れられたこの施設で、監禁中に死亡した患者は22名にのぼります。山井道太という患者は、洗濯作業に長靴を要求し、長靴がないと仕事ができないという態度をとったことを理由としてこの重監房に送られています。
WHO西太平洋地域らい専門官として世界各国のハンセン病患者の状況を見てこられた犀川一夫先生は、熊本地裁でこう証言しました。
日本ほど、ハンセン病患者の後遺症が重篤な国はない。患者作業のせいです。
療養所内では結婚は認められていましたが、夫婦が同居するためには、男性は断種手術を受けなければなりませんでした。妊娠すると、堕胎を強いられました。療養所には、つい数年前まで、堕胎された胎児の標本がホルマリン漬けで保存されていました。そのなかには、実は新生児として生まれた子どもも含まれていたのではないかという疑いがあります。
らい予防法の廃止と国賠訴訟の提起
1996年4月、らい予防法の廃止に関する法律の施行により、らい予防法は廃止されました。
隔離政策が終わっても、元患者たちにとって、隔離政策によって失われた日々は帰ってきません。それをどのように補償するかは、法廃止に伴う大きな課題であったはずでした。しかし、国は法廃止後も療養所を残し、引き続き療養所での生活を希望する元患者たちの生活を保障するだけで、隔離政策による被害の回復には、何らの政策も準備しませんでした。
九州の弁護士たちがこの問題に気がついたのは、当時、鹿児島の星塚敬愛園に在園していた島比呂志さんの、けんりほうニュースに対する投稿「法曹の責任」がきっかけでした。これを契機として九州弁護士会連合会の人権擁護委員会が調査を開始、星塚敬愛園をはじめとして、菊池恵楓園(熊本)、奄美和光園、沖縄愛楽園、宮古南静園といった九州各地での被害聴き取り、法律相談といった活動が開始されました。そして、1996年6月、1998年2月の2度にわたるシンポジウムを経て弁護団が結成され、同年7月31日、熊本地方裁判所にらい予防法違憲国家賠償請求訴訟(以下、「ハンセン病訴訟」と略称します)が提起されました。
当事務所からは、当時10年目の弁護士であった久保井と小林とが弁護団に参加しています。
原告団の拡大
提訴時、弁護団は「石にかじりついても3年解決」を宣言しました。原告たちの平均年齢からしても、長期化は許されない裁判でした。
何よりもまず必要だったのは原告団の拡大でした。第1次提訴に参加した原告は、星塚敬愛園から9名、菊池恵楓園から4名、合計13名。全国13園に約4500名が在園しているというのに、原告がたった13名というのでは、この問題の大きさを裁判所に理解させることはできません。
弁護団は、各地の療養所を飛び回り、国賠訴訟の意義を語って訴訟への参加を呼びかけました。もちろん全国13の療養所の在園者を全て九州の弁護団で担当できるはずはありません。HIV弁護団、水俣病弁護団、青法協など様々な繋がりで各地の弁護士に声をかけ、この問題への取り組みを要請しました。その結果、東京の弁護士を中心とする東日本弁護団、大阪・兵庫・岡山の弁護士から構成される瀬戸内弁護団が結成され、それぞれの地域の療養所へ入っていくことになります。
原告数の増加は、当初、極めて緩やかなものでしかありませんでした。裁判に立ち上がることによって社会にいる親族に迷惑がかかるのではないか、国の責任を追及することによっていまの療養所生活が危うくなるのではないか、そういった様々な心配が、在園者を躊躇わせていました。無関心を装う在園者はまだしも、中には裁判に対して露骨な嫌悪感を示す在園者もいました。後に熊本地裁の法廷で青木美憲証人が証言しますが、壁の中に閉じ込められた人間は「はじめは壁を憎み、やがて壁に慣れ、ついには壁に依存する」といいます。この当時の療養所は、壁に依存して生きていく者の諦観に支配されているように見えました。90年間にわたって国の政策を許してきた社会全体への不信感が、諦めを強いていた面もあったと思われます。
このような状況を大きく変えたのは、瀬戸内海に浮かぶ大島青松園からの大量提訴でした。そして、沖縄愛楽園からの大量提訴がそれに続きます。東京地裁、岡山地裁への提訴者も増え続け、13人の原告でスタートしたハンセン病訴訟の原告は、2000年6月の時点で三地裁合計549人を数えるまでに拡大しました。
画期的な熊本地裁判決
2001年5月11日に下された熊本地裁判決は、隔離政策の被害を真正面から捉え、厚生省の政策責任のみならず国会の立法不作為責任まで認める画期的なものでした。
隔離による人権侵害を判決はこう表現します。
ある者は、学業の中断を余儀なくされ、ある者は、職を失い、あるいは思い描いていた職業に就く機会を奪われ、ある者は、結婚し、家庭を築き、子供を産み育てる機会を失い、あるいは家族との触れ合いの中で人生を送ることを著しく制限される。
人として当然に持っているはずの人生のありとあらゆる発展可能性が大きく損なわれるのであり、その人権の制限は、人としての社会生活全般にわたるものである。
そしてこれは単なる居住・移転の自由の侵害という理解で正当に評価できるものではなく、むしろ憲法13条に根拠を有する人格権そのものに対する侵害である、と判決は断じました。
また原告の方々が苦しんできた差別・偏見の原点は、無癩県運動などの戦前のハンセン病政策によるものであり、さらに戦後の徹底した患者収容策、患者宅の消毒、「お召し列車」(ハンセン病患者強制収容専用の車両)による患者輸送などが、患者に対する偏見を助長したことを認め、「ハンセン病に対する差別・偏見は古来からのものであり法や政策が原因ではない」という国側の主張を退けました。
このような「人権を著しく侵害する内容を有し、ハンセン病に対する差別・偏見を助長、維持するという弊害をもたらし続けたところの新法(らい予防法)の下での隔離政策」が平成8年の法廃止まで継続されたというのが判決の認定です。
隔離政策の必要性に関しては、「そもそもハンセン病は、感染し発病に至るおそれが極めて低い病気」であること、及びそのことが「新法制定(1953年)よりはるか以前から政府やハンセン病医学の専門家において十分に認識されていた」ことを、判決は至るところで強調しています。また1940年代に登場した特効薬スルフォン剤に関しても、「これまで確実な治療手段のなかったハンセン病を『治し得る病気』に変える画期的な出来事であった」とその歴史的意義を大きく評価しました。
こういった事実認定に基づき、判決は1960年以降も隔離政策を継続し続けた厚生大臣の行為、及び1965年以降もらい予防法を廃止しなかった国会の立法不作為を、国家賠償法上違法であると評価したのです。
国会の立法行為については、当時、「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合」に限り国家賠償法上違法と評価されるというのが最高裁判例(在宅投票制度廃止に関するもの)でした。
熊本地裁判決は、その判例について「もともと立法裁量にゆだねられているところの国会議員の選挙の投票方法に関するものであり、患者の隔離という他に比類のないような極めて重大な自由の制限を課する新法の隔離規定に関する本件とは、全く事案を異にする」、その違法性判断基準は「論拠として、議会制民主主義や多数決原理を挙げるが、新法の隔離規定は、少数者であるハンセン病患者の犠牲の下に、多数者である一般国民の利益を擁護しようとするものであり、その適否を多数決原理にゆだねることには、もともと少数者の人権保障を脅かしかねない危険性が内在されているのであって、右論拠は、本件に全く同じように妥当するとはいえない」と論じ、本件は最高裁判例にいうところの「容易に想定しがたいような極めて特殊で例外的な場合」として違法性を認めるべきだとしました。
劇的な控訴断念
判決が言い渡されたその時、国会ではちょうど就任したばかりの小泉総理に対する代表質問の真っ最中でした。判決が国会に伝わると、即座に「この判決をどう受け止めるか」という質問がなされ、議場に拍手が沸き起こったと報じられています。
その直後、原告団・弁護団は控訴断念を求める闘いに突入。判決が国会の責任を認めたことはこの闘いの大きな武器になりました。国会の責任を認めた判決に控訴するかどうかは国会の意思を尊重すべきだ、控訴するかどうかを国会で議論せよ、というのが原告団・弁護団の攻め筋です。
一方、法務省・厚生労働省・財務省などの官僚の巻き返しも凄まじく、その意を受けた与党三党は「ハンセン病問題の最終解決を求める議員懇談会」の提案する「控訴しない旨の決議」を阻止、法務省から衆参両議員宛の控訴に関する意見照会にも「回答留保」で抵抗しました。14日の段階で原告との直接面談に応じ、その被害の訴えに涙した坂口厚生労働大臣は、控訴を主張する厚生労働官僚から孤立に追い込まれ、一時は辞意表明まで報じられました。
控訴断念を求める闘いは、永田町と霞ヶ関だけで繰り広げられていたわけではありません。東日本・瀬戸内・西日本の各弁護団は、判決直後から、控訴を断念させるための大規模掘り起こしがを開始しました。北は青森から南は沖縄の石垣島まで、100名近くの弁護士が、飛行機・電車・バス・タクシー・連絡船を乗り継いで集めに集めた委任状はその数なんと923通!
その結果、判決時に熊本・東京・岡山三地裁合計779人だった原告団は、判決から10日後には1702名にまで膨れ上がったのです。
三地裁同時に大量追加提訴が行われた5月21日、総理官邸前には全国から100名以上の原告が結集し、市民や国会議員の支援を得ながら、小泉総理との直接面談を求める座り込みを決行しました。国会でも閣議でも、「総理は原告と面談すべし」との声が相継ぎました。
原告と小泉総理との面談が実現したのは5月23日の午後4時、そしてこの日の午後6時、小泉総理は控訴断念を表明しました。
国会の立法不作為の違法性を認めた判決が確定したのは、史上初めてのことでした。
判決確定後の闘い
判決確定後は、5月25日に発表された「ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話」に基づき、ハンセン病補償法が制定されるとともに、在園保障、社会復帰支援、謝罪・名誉回復、真相究明などの課題を実現するためのハンセン病問題対策協議会が設置されました。主戦場は、法廷からこの協議会へと場所を移します。
このハンセン病問題対策協議会での合意により、社会内で生活している退所者の生活を支援するための退所者給与金や二度にわたる厚生労働大臣名義での謝罪広告などが実現しました。また、協議会の合意によって設置された「ハンセン病問題に関する検証会議」は、22年半にわたって検証作業を実施し、国賠訴訟では明らかにならなかったより深い被害実態を明らかにしました。
一方、法廷での闘いも終わったわけではありません。熊本地裁判決やハンセン病補償法は、療養所への入所歴があり、かつ、生存している被害者のみを対象とするものであり、判決確定後も、非入所原告及び遺族原告の裁判闘争が残っていました。この闘いは、熊本地裁による和解勧告を経て、2001年1月の基本合意で決着しました。
さらに、2003年12月からは第二次世界大戦中に日本が朝鮮に設置したハンセン病療養所ソロクト更生園の入所者から、ハンセン病補償法に基づく補償請求が行われ、台湾楽生園の入所者もこれに続きます。これに対する不支給決定を不服として、2004年8月にはソロクト更生園・台湾楽生園補償請求訴訟が東京地裁に提起されました。
この訴訟は、2005年10月25日、東京地裁民事第3部がソロクト更生園訴訟について請求棄却の判決を下し、その30分後、同じ法廷で同民事38部が台湾楽生園訴訟について請求認容判決を下すという劇的な展開を見せます。そして、同年12月、厚労省は、日本の植民地時代における朝鮮、台湾のハンセン病療養所入所者を、日本国内の療養所入所者と同様の条件で補償する方針を表明し、翌2006年2月、ハンセン病補償法が改正されました。
日本政府が、第二次世界大戦中に行った行為に関し、個人に対して補償を行うという立法はこれが唯一のものと思われます。
残された課題
ハンセン病隔離政策被害者たちの闘いは、時代や地域を超えた拡がりを見せました。しかし、それは被った被害の甚大さに見合うものではありません。解決しなければならない課題は、数多く残されています。
2003年11月に起こった菊池恵楓園入所者に対するアイレディース宮殿黒川温泉ホテルの宿泊拒否事件は、ハンセン病に対する偏見・差別が根強く残っていることを明らかにするものでした。また、2011年には、市民団体による憲法劇「ドクター・サーブ」の中でのハンセン病患者の描写が差別・偏見を助長するものではないかと物議を醸しました。ハンセン病に関する正しい知識と、それに対する差別・偏見の歴史を広く伝えていく努力は、まだまだ必要とされています。
最大の課題は、療養所で終生を過ごすしかなくなってしまった被害者の方々の生活をどう保障していくのか、という問題です。
ハンセン病問題対策協議会では、「13の国立ハンセン病療養所入所者が在園を希望する場合には、その意思に反して退所、転園させることなく、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努める」ことが確認されています。しかし、入所者の減少と高齢化は否応なく進み、療養所はかつてのようなコミュニティーとして機能し得なくなりつつあります。また、公務員定数削減政策の中、入所者が減少していく療養所にマンパワーを確保することが極めて困難になっています。
このような状況の中、療養所の入所者を構成員とする全国ハンセン病療養所入所者協議会は、療養所の将来構想を実現するために、「らい予防法の廃止に関する法律」を廃止し、新たに「ハンセン病問題基本法」を制定しようという方針を提起し、2007年8月から、「ハンセン病療養所の将来構想をすすめる会」による100万人署名運動が始まりました。
基本法制定を求める署名活動は開始から9ヶ月で93万筆に達し、2008年6月、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定されました。この法律には、ハンセン病問題基本法として求めてられていた内容がほぼ全面的に含まれており、私たちはこれを「基本法」と呼び習わしています。
この通称基本法に基づき、これまでの制度ではできなかった一般の入院患者の受入れや、敷地内への幼稚園誘致などが実現しています。また、ハンセン病療養所職員については、事実上、公務員定数削減計画の対象から外すことが合意されています。しかし、労働条件の劣悪さなどから、マンパワー不足は、いまだ解決できていません。
2011年6月に厚労省前に建立された碑には、次のような言葉が刻まれています。
ハンセン病の患者であった方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、深く反省し、率直にお詫びするとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の念を捧げ、ハンセン病問題の解決に向けて全力を尽くすことを表明する。
「ハンセン病問題の解決」とは、隔離政策の被害者たちの、人間の尊厳を回復することです。残された僅かな年月、彼らに尊厳を保った生活を保障することは、国として最低限の務めであるとわたしたち私たちは考えています。
ハンセン病問題の解決のために、みなさまのご理解とご支援をお願いいたします。