定子は、藤原道隆の長女として、貞元元年(976年)に生まれています。康保年間(964〜967年)生まれと推定される清少納言より10歳程年少になります。
父道隆は、後期摂関政治を確立した藤原兼家の長男で、その弟に、粟田殿道兼、後の御堂関白道長がいます。もう一人の腹違いの弟が、右大将道綱。つまり、道綱母は、兼道の側室であり、若き日の道隆も、蜻蛉日記にその姿を見せています。
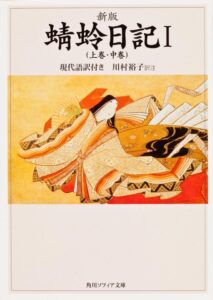 かくなむと見つつ降るほどに、ある日の昼つかた、大門のかたに馬のいななく声して、人のあまたあるけはひしたり。木の間より見通しやりたければ、姿、直人あまた見えて歩み歩みあり。「兵衛佐なめり」と思へば、大夫より出して、「今まで聞こえさせざりつるかしこまり、取り重ねてとてなむ、参り来たる」と言ひ入れて、木陰に立ちやすらふさま、京おぼえていとをかしかめり。
かくなむと見つつ降るほどに、ある日の昼つかた、大門のかたに馬のいななく声して、人のあまたあるけはひしたり。木の間より見通しやりたければ、姿、直人あまた見えて歩み歩みあり。「兵衛佐なめり」と思へば、大夫より出して、「今まで聞こえさせざりつるかしこまり、取り重ねてとてなむ、参り来たる」と言ひ入れて、木陰に立ちやすらふさま、京おぼえていとをかしかめり。
(蜻蛉日記 一二四段)
兼道の不実に怒って鳴滝の般若寺に籠もってしまった道綱母を迎えに来た道隆。その姿をみて都のことを思い出した、というのですから、都会風のお洒落なファッションだったんでしょうね。
わたしが大好きな逸話は、兼家の六十の賀で、舞う予定になっていた甥の福足君(粟田殿道兼の子)が駄々を捏ねてみんなを困らせている時に、道隆が舞台に上がって甥と一緒に舞い、事態を収拾したというものです。
…「あれは舞はじ」とて、びんづらひき乱り、御装束はらはらとひき破りたまふに粟田殿、御色真青にならせたまひて、あれかにもあらぬ御気色なり。ありとある人、「さ思へることよ」と見たまへど、すべきようもなきに、御をぢの中関白殿道隆、おりて舞台に上らせたまへば、言ひをこづらせたまふべきか、又にくさにえ堪へず、追ひおろさせたまうべきかと、かたがだ見はべりし程に、この君を御腰の程にひきつけさせたまひて、御手みづからいみじう舞あせはまひたりしこそ、楽もまさりおもしろく、かの君の御恥もかくれ、その日の興もことのほかまさりたりけれ。祖父殿兼家もうれしと思したり。父おとど道兼はさらなり、よその人だにすずろに感じ奉りけれ。
(大鏡 右大臣道兼)
こういったお洒落で機転の利いた道隆が妻として選んだのが、大和守高階成忠の娘、高階貴子でした。当時、円融帝に内侍として仕え、才媛の誉れ高かった女性です。
内侍というのは、天皇に近侍して、奏上や宣下を仲介する内侍所に仕える女官の総称で、その長官の尚侍(ないしのかみ)や、次官の典侍(ないしのすけ)は、天皇の非公式な側室という面もあるようですが、高階貴子の場合は、その下の掌侍(ないしのじょう)であり、純粋な秘書官と思われます。
帝の御時に、おほやけ宮仕に出し立てたりければ、女なれど、眞字などいとよく書きければ、内侍になさせ給ひて、高内侍とぞ云ひける。この中納言殿、萬に戯れ給ひける中に、人よりことに志ありて思されければ、これをやがて北の方にておはしける程に、女君達三四人、男君達三人出で來給ひにければ、いといみじきものに思しながら、猶御戯れはうせざりければ、この御子どもと云はれ給ふ公達數多になり給へど、猶このむかひばらの、いみじきものに思ひ聞え給へるうちに、母北の方の才などの、人より異なりけれにばにや、この殿の男君達も女君達も、皆御年の頃よりはいとこよなうぞおはしける。
(栄華物語第参 さまざまのよろこび)
母上は高内侍貴子ぞかし。されど、殿上えせられざりしかば、行幸、節会などには南殿にぞ参られし。それはまことしき文者にて、御前の作文には文奉られしとはよ。少々のをのこには勝りてこそ聞こえはべりしか。
(大鏡 内大臣道隆)
平安時代における公的な文学は、まずは漢詩文です。「眞字などいとよく書きければ」というのは、当時、「女手」といわれていた平仮名ではなく、漢字を使いこなせる女性であったということ、「それはまことしき文者にて、御前の作文には文奉られし」というのは、漢学に優れ、行幸、節会といった機会には、南殿(紫宸殿)に伺候して漢詩文を披露したということですね。
そこいらの男性では太刀打ちできないくらいだったらしい、と大鏡は伝えています。
彼女は、漢詩の才だけではなく、歌にも秀でていました。今日、私家集は伝わっていませんが、いくつかの歌が勅撰集に残されており、百人一首にも、儀同三司母の名で、道隆が通い始めた頃の歌が選ばれています。
中関白通ひそめけるころ
わすれぢの 行末までは かたければ けふをかぎりの 命ともがな (新古今1149)
この時代、多くの女性は、職務上の肩書きや、身内の男性との血縁関係で呼ばれており、内親王あるいは摂関家の娘以外に、実名が伝わっている女性はほとんどいません。清少納言も、紫式部も、実名は不明です。
高内侍や儀同三司母という呼称以外に、「貴子」という名前が知られていることは、この女性が、それだけ特別な注目を集めていたことを示すものでしょう。因みに、もう一人の例外は、藤原賢子つまり紫式部の娘である大弐三位。
こういった女性を、道隆は見初め、正室(北の方)に迎えました。父兼家も、伊勢守藤原倫寧の娘を妻として道綱を儲けましたが、それはあくまで側室でした。いくら才媛とはいえ、受領階級の娘を正室に迎えたところに、道隆の新しさがあります。
そして、この新しさは、その長女である定子にも、確実に受け継がれていました。
…二月には内大臣殿の大姫君、内へ参らせ給ふ有様、いみじうののしらせ給へり。殿の有様、北の方など宮仕にならひ給へれば、いたう奥ぶかなる事をば、いとわろきものに思して、今めかしう氣近き御有様なり。
(栄華物語第参 さまざまのよろこび)
清少納言が出仕したのは、奥ゆかしさといった伝統的な価値観よりも、新しさ、親しみやすさを大切にする、そんな定子のサロンでした。
清少納言が才芸女房のはしりであるとすれば、受領階級の歌人清原元輔の娘にその可能性を見出したのは、同じく受領階級出身であった貴子の炯眼だったのではないでしょうか。そして、それは、紫式部、和泉式部、そして後の菅原孝標女といった受領階級の子女たちが大活躍する王朝文学の最盛期に繋がっていきます。
